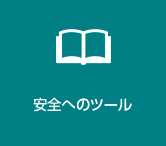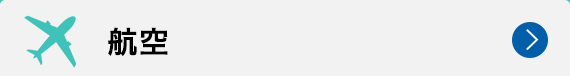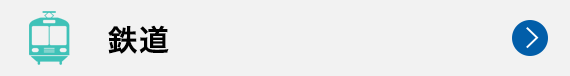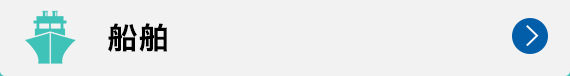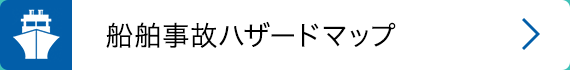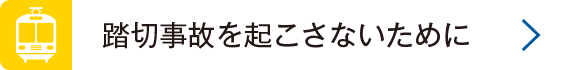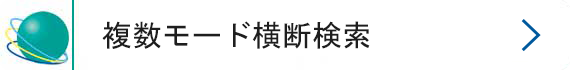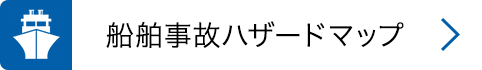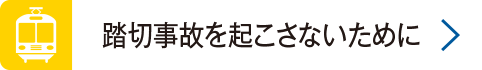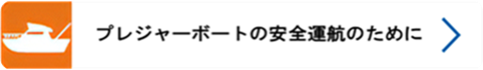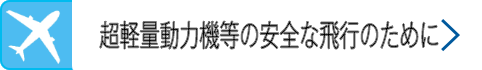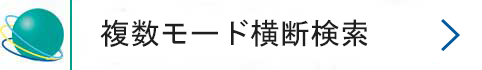概要
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 監視取締艇おりおん乗揚(のり養殖施設) |
| 発生場所 | 兵庫県明石市江井ケ島港南西方沖 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位203°2,610m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、江井ケ島港南西方沖で行っていた漁船の立入検査業務を終え、阪神港神戸区へ向けて帰航を開始した。 船長は、操舵室右舷側の座席に腰を掛け、両舷主機を回転数毎分2,000の半速力前進として約15ノットの速力で東進中、平成27年5月10日19時25分ごろ、本船が後方に引っ張られる感じがして微速力前進としたところ、プロペラ翼付近で異音がしたので、主機のクラッチを中立とした。 船長は、本船の行きあしが止まり、次いで後方に動き始めたので、両舷主機を停止し、停船したのちに周囲を見たところ、俵型の浮き(漁具)が左右に見えたので、のり養殖施設に乗り入れ、プロペラ翼に幹綱が絡まったことを知った。 船長は、両舷主機を後進に掛けて抜け出そうと試みたが、本船が動かず、船尾端から海中を見たものの、プロペラ翼に幹綱が絡んだ状況が見えなかったので、海に入って幹綱の絡みを解こうと考えたが、北風が強く、波高約1mの波があり、また、水温が低いので、危険であると判断し、海上保安庁に救助を要請した。 船長は、風浪を受けて本船が圧流されることを防ぐため、北風を受けて船首が南に向いた状態となった本船の船首及び船尾から幹綱に索を渡して船固めを行い、救助を待っていたところ、船尾が左方へ振れ、幹綱が本船から離れた所に見えたので、幹綱の絡みが解けたものと判断し、自力で航行してのり養殖施設から抜け出すこととした。 本船は、両舷主機を始動したところ、左舷主機が使用可能であったので、船長が、船尾で船固めを外す指揮をとり、他の乗組員に操船を委ねて阪神港神戸区へ帰った。 船長は、翌日、のり養殖施設の管理者に本事故の発生を連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、風速約10m/sの北風及び波高約1.0mの波を受ける状況下、江井ケ島港南西方沖を阪神港神戸区に向けて航行中、船長が、船首目標への針路を保持することに意識を向けていたため、のり養殖施設の区域を示す標識灯の灯火及び漁具に気付かず、のり養殖施設に進入して乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
- ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。
《船舶事故報告書のまえがき》
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
《船舶インシデント報告書のまえがき》
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
《参考》
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。
- 断定できる場合は「認められる」
- 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
- 可能性が高い場合は「考えられる」
- 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
- ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
- ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
- ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。