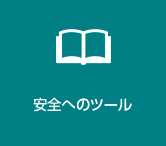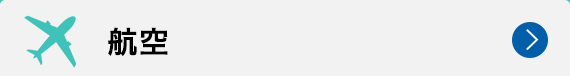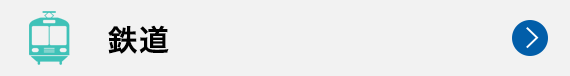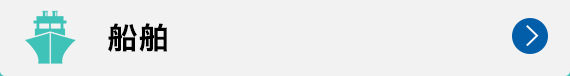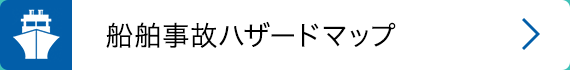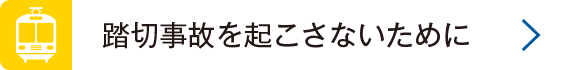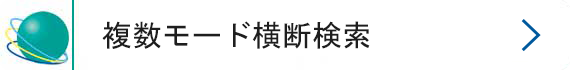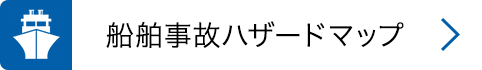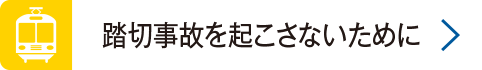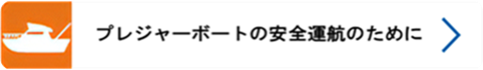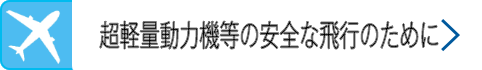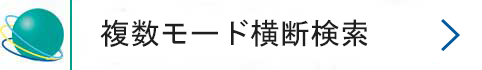概要
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船瑞穂丸起重機船第三瑞穂丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 鹿児島県志布志市志布志港 志布志港防波堤灯台から真方位239°430m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長、機関長、一等機関士、甲板員A、甲板員B及び機関員Aが乗り組み、船首部をB船船尾凹部と嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を形成して志布志港の志布志大橋前の岸壁に左舷着けで係留し、‘クレーンの運転を担当する一等機関士’(以下「クレーン士」という。)がB船船首部に備えられたクレーンを操縦して岸壁上の石材の積荷役を行い、平成23年12月15日10時25分ごろ荷役を終了したが、重さ約150kgの石材が船倉外の両舷通路に1個ずつ落ちていたので、クレーンのブームからワイヤで吊り下げられていたバケットを使用して船倉に戻すことにした。 機関長は、右舷側通路の石材にワイヤロープを巻き、シャックルでバケットの爪の穴(直径約40mm)にワイヤロープをつなぎ、バケットで同石材を持ち上げることとし、甲板員Bと同通路の石材にワイヤを巻いたのち、船尾方に離れ、クレーン士がバケットを石材近くに移動させるのを待った。 船長は、訪船者の来船予定時刻が迫っていたので、岸壁に舷梯を掛けるため、機関員Aと両舷船尾のウインチを操作してA船押船列船尾を岸壁に寄せる作業に当たり、また、甲板員Aは甲板室船尾方で水撒きの準備をしており、3人とも右舷側通路での作業を見ていなかった。 クレーン士は、ブームを上げてバケットを船倉越しに右舷側通路の外縁まで移動させ、バケットを約1.5m降ろし、続いてゆっくりとコーミング方に寄せたところで、機関長の合図によりブームを下げる操作に移行した。 クレーン士は、機関長が左手の拳を差し上げ、「ストップ」と合図したので、操作レバーを止め、更に操縦席左方のスイッチパネルを向いてパーキングブレーキのスイッチを入れてブームの旋回動作を電気的に停止した。 クレーン士は、バケットに視線を向けた際、バケットがゆっくり機関長に接近し、機関長をコーミングとの間で挟んだように見えたので、クレーンを離れて機関長の所に向かった。 甲板員Bは、右舷側通路後方において、クレーンのブーム及びバケットの動きを見ていたところ、機関長が、「ストップ」の合図を行ったと同時に石材に向かい、10時38分ごろ、バケットとコーミングの間に入ったとき、ゆっくりと揺れてコーミングに接近していたバケットとコーミングとの間に機関長の胸部が挟まれたのを見た。 機関長は、バケットが揺れてコーミングから離れたところ、立った状態から、頭を船尾方にしてうつ伏せ状態で右舷側通路上に倒れた。 甲板員Bは、頭部をやや舷外に垂らしていた機関長に近寄って「大丈夫ですか」と声を掛けたが応答がなく、右舷船尾でウインチ操作をしていた機関員Aに向かって「救急車をお願いします」と叫んだ。 船長は、救急車を手配し、救急車が到着するまでの間、クレーン士が右舷側通路で機関長を仰向けにして心臓マッサージを行った。 機関長は、心肺停止の状態であり、救急車により病院に搬送されたが、11時27分死亡が確認された。 死因は、心臓破裂と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、志布志港で石材積込後、右舷側通路に落ちていた石材をクレーンのブームからワイヤで吊り下げられていたバケットを使用して船倉に戻す作業中、クレーン士が、石材付近のコーミングにバケットを寄せたのちにブームを下げていたが、機関長の合図でブームを下げる操作を止めた際、機関長が、バケットとコーミングの間に入ったため、コーミングに向けて揺れていたバケットとコーミングの間に胸部を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
- ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。
《船舶事故報告書のまえがき》
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
《船舶インシデント報告書のまえがき》
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
《参考》
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。
- 断定できる場合は「認められる」
- 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
- 可能性が高い場合は「考えられる」
- 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
- ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
- ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
- ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。