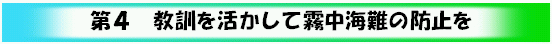 |
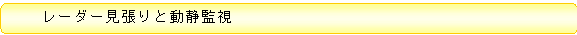 |
| 霧中での衝突原因をみると,「近距離に接近するまで又は衝突まで相手船に気付かなかった」ものが2割,「一度は相手船の映像に気付いていたものの,相手船の動静を十分に把握していなかった。」ものが3割となっていて,両者を合わせた「レーダー見張り不十分」が5割を占めています。 |
 |
|
この中には,「感度調整や海面反射の除去といったレーダーの調整が不十分であった。」,「レンジの切り換えを行わなかったので相手船の探知が遅れた。」など,画面の調整や操作に問題があった事例や,レーダープロッティングなど系統的な映像の観察による動静監視ができていなかった事例が多く見受けられます。
また,霧中で衝突した船舶の大部分が,自動衝突予防援助装置(ARPA:アルパ)が付いていないレーダーを使用していました。 |
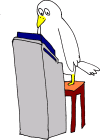 |
|
| このような船舶では,相手船のレーダー映像が船首輝線のどちら側にあるかを見て,映像がない方向に転針し,その映像を船首輝線の同じ側に見るように小刻みに転針を繰り返すケースが多く見受けられます。小刻みの転針では,相手船がレーダーでそのことを判別することが難しいことを念頭に置いていて下さい。 |
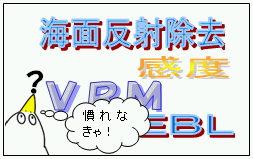 |
|
また,反航船の映像が船首輝線を横切るように近付いてくる場合は,相手船の針路は映像の移動方向よりも船首輝線寄りを向いていますし,自船が相手船の映像を右(左)舷船首に見ているときは,相手船は自船の映像を左(右)舷船首に見ていることになります。そのため,互いに映像がない方向に転針すると,両船が同じ方向に転針することになり,衝突の危険を生じるおそれがあることに注意して下さい。
最近では,アルパ付きのレーダーを搭載した船舶も増え,また,電子プロッティング機能や自動物標追跡機能が付いたレーダーの搭載船も多くなって,他船の動静を監視する上で随分便利になりました。しかし,折角の機能を十分に活用できていない事例や,アルパで最接近距離(CPA)を確認したことで安心してしまい,その後の動静監視を怠って衝突した事例もありました。衝突の危険がなくなるまでレーダー映像の監視を続けて下さい。 |
| そして,是非ともこの機会に,実際の針路とレーダー映像の動きとの違いなど,レーダー映像を観察する上での基本的なことを確実に理解し,レーダーの操作はもちろん,各種機能の活用方法にも慣れて動静判断の技量を向上させて下さい。 |
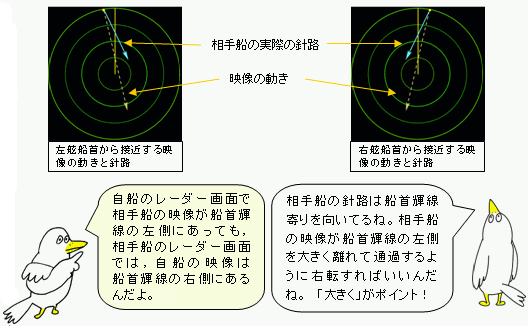 |
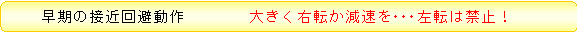 |
衝突原因の中で「レーダー見張りが不十分」が5割であるのに対し,「レーダー見張りは行っていたものの,著しく接近する状況下で大幅な減速や行きあしを止めるなどの適切な避航措置をとらなかった。」ものも5割を占めています。
相手船の映像に方位変化がなく衝突のおそれがある場合や,少しの方位変化があるものの,著しく接近する状況となったときには,早期に接近回避のための動作をとらなければなりません。大きく右転して相手船との通過距離を十分にとることが第一ですが,右舷側に同航船や陸岸があるため右転ができないときには,減速して相手船の通過を待つことも選択肢の一つです。しかし,接近回避動作をとるに当たって,右転も減速もできないようなやむを得ない場合を除いて,左転は禁止されていることを忘れてはいけません。
|
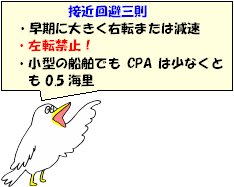 |
海難事例の中に,CPAが0.3海里では,危険や不安を感じて転舵したケースが数件ありました。このことから,「CPAが0.3海里以内は危険距離」と見ることができ,小型の船舶でもCPAを少なくとも0.5海里は確保することが必要ですし,広い海域ではCPAを
0.75〜1.0海里とって通過することが衝突防止に繋がります。 |
|