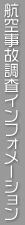 |
|
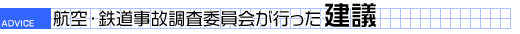
 |
| 日本航空株式会社所属ダグラスDC8−61型JA8061の航空事故に係る建議 |
 |
(1982.12.23建議)
(JA8061 東京国際空港 S57.2.9 発生事故) |
 |
- 航空機の運航規程等の遵守
日本航空株式会社は航空法第104条の規定に基づき運輸大臣の認可を受けて航空機運航規程を定めているほか、運輸省航空局技術部運航課長の承認を得て航空機運用規程(Aircraft Operation Manual)を定めている。同社の運航乗務員はこれら両者の定める諸規程を遵守すべきことが期待されているところ、本件事故にあっては操縦室用音声記録装置の記録によれば、事故直前の着陸進入時に当該事故機の運航乗務員が航空機運用規定の定めるとおりのコールアウトを行っていない部分のあることが認められた。
航乗務員も人間である以上、飛行中にいわゆる「うっかりミス」を起こすこともあり得るし、また、何等かの理由で不意に機能喪失に陥ることもあり得ないことではない。しかも、これらは、離着陸時や緊急事態発生時のようにストレスの高まる場合に起こりやすいものであることに加えて、このような時には対応措置を講じるための時間が極めて限られているので、これら運航乗務員の「うっかりミス」や機能喪失に他の運航乗務員が一刻も早く気がつくことが、危険や事故を回避するための必要不可欠な前提要件となる。しかしながら、いつ生ずるかも知れないこれらに対して、対応措置が間に合うように前広に他の運航乗務員が気がつくようにするためにはどうすれば良いかということは、なかなかその解答を見いだし難い問題であって、各国政府関係当局も空港企業も苦心しているところである。
だが、離着陸時に例えば必ず行わなければならないコールアウトを常日頃から厳格に励行せしめて置いて、少しでもこれが正確に行われなかった時には何等かの異常があるのではないかと考えて、他の運航乗務員が直ちに何等かの適切な措置をとるようにして置くということは、離着陸時というようなクリティカルな飛行局面において運航乗務員の「うっかりミス」や突然の機能喪失に伴う危険や事故を回避するための唯一と言って良い有効な手段であると考えられている。
今回の事故の場合も、例えば羽田への着陸進入中の最終段階において副操縦士の「ファイブ・ハンドレッド」のコールアウトに対して機長が航空機運用規程の定めるとおりの応答をしなかったとき、常日頃から厳格に航空機運用規程が遵守されていてコールアウトも定められたとおりに行わなければ異常が生じたのかも知れないと直ちに考えるが当たり前というような状態にあったならば、この段階で何等かの適切な措置が取られ得たかも知れない。
航空機運航規程等の定めるところに従ってコールアウトをし、操作を行うことは、航空機運航中の運航乗務員の過誤をなくし、その突然の機能喪失にも適切に対応し得るようにして航空機の安全な運航を確保するための必要欠くべからざる運航乗務員による共同行為である。
日本航空株式会社は、その過去の幾つかの航空事故について関係国の航空事故調査当局より手順や規定類の遵守に言及した指摘や勧告を受けており、わが国の運輸省航空局からも繰り返して航空機運航規程等を厳格に遵守せしめるよう指導されて来たところであるが、あらためて、その運航乗務員に航空機運航規程を遵守しなければならない理由を十分に理解せしめるとともに、その形式的なものではなく厳格な励行の一層の強化に資するための必要な措置を講ずるべきである。
(注)日本航空株式会社にあっては、古くは、サンフランシスコ沖合いに不時着水したDC−8−62型JA8032に係る昭和44年12月31日付け米国運輸安全委員会事故調査報告書中で副操縦資による定められたコールアウトが行われていなかったことの指摘があり、「この事故の推定原因は、オートパイロット連動進入を実施するための規定された方式の不適正な適用によるものである。」と結論されている。
最近では、ニューデリーで墜落したDC−8−53型JA8012に係る昭和48年4月30日付けインド政府事故調査報告書において「本事故の直接原因は、滑走路を視認することなく、またすべての計器指示を確認しなかった運航乗務員の定められた手順の無視によるものと推定される。」とされ、モスクワで墜落したDC−8−62型JA8040に係る昭和48年7月6日付けソ連邦民間航空省事故調査委員会事故調査報告書において「航空機乗務員は航空機のシステムの使用に関する所定の規則を遵守するよう措置する・・・こと」を勧告されている。さらに、クアラルンプールで墜落したDC−8−62型JA8051に係る昭和55年1月23日付けマレイシア民間航空局事故調査報告書において「North Markerにおいて、滑走路を視認できないときは、進入復行するようにとの公示及びJALの運航方式に反していた。」と指摘されている。
- 運航乗務員に係る健康管理の改善
今回の航空事故の調査を通じて、日本航空株式会社の運航乗務員に係る健康管理には例えば運航乗務員健康管理室の責務、権限、事故処理方法等が社内規程上明確になっていない等の不具合が認められた。
他方、運輸省航空局においては、事故直後に日本航空株式会社の立入検査を行い、その結果見いだされた問題点を指摘し、所要の改善措置をとるよう同社に勧告を行い、同社は、逐次運航乗務員健康管理室の改善等の措置を実施してきている。
当委員会は、確かにこれらの改善措置の実施により日本航空株式会社における運航乗務員の健康管理に関する制度は、今まで以上に充実強化されつつあるものと考える。しかしながら、かかる制度が整備されたとしても、それば有機的に十分機能しなければ、運航乗務員の心身の不調が関係する航空事故の再発防止は規しがたい。かかる制度が効果的に機能し得るよう広い意味で運航乗務員と関係医師との間の信頼関係の確立を図り、航空の安全には寄与するが当該乗務員にとっては不利となるようなことでも運航乗務員及びその家族・同僚・上司等が医師に申告し易くするための物心両面にわたる環境づくりをすることも肝要であって、そのための必要な措置を講ずるべきである。
|
 |
|